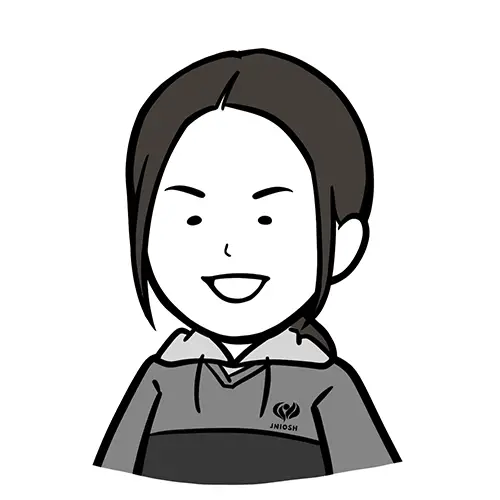研究員に聞いてみよう! 「つながらない権利」編 File#2
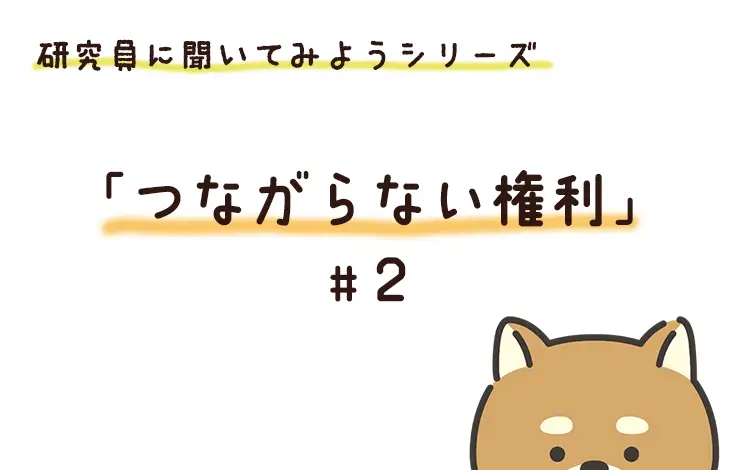
研究員に聞いてみよう
なんとなく聞いたことはあるけど、よく分からない。愛想笑いで流してしまう。そんなトピックについて、RECORDsメンバーに教えてもらうシリーズです。
今回はこちら
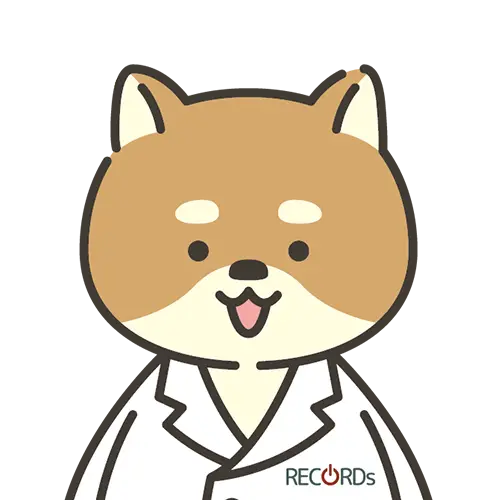
こんにちは、あんえい犬です。
今回は、「つながらない権利」の続きです。
はじめての方は、まず→「File#1」をご覧ください。

こんにちは。久保(上席研究員)です。今回もよろしくお願いします。
さっそく、「つながりすぎる」ことの問題点について、お話するね。
やはり、オンとオフのメリハリがつきにくくなってしまったことでしょう。
働く人々の疲労の回復、ストレスの解消には勤務時間外には仕事から物理的には離れるだけではなく、心理的にも離れることが重要だと言われています。
これを専門用語では「サイコロジカル・ディタッチメント(心理的距離)」と呼びます。
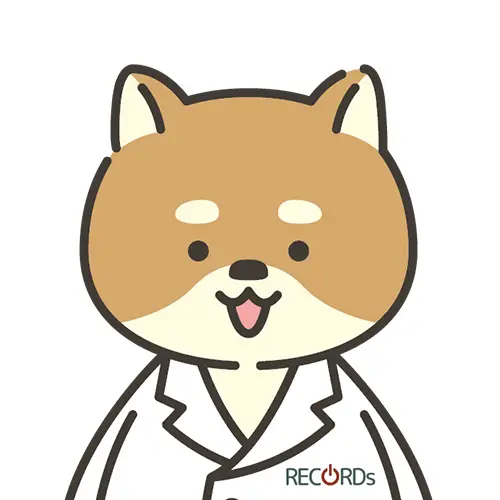
あんえい犬
サイコロ・・・
ただ休めばいい、というわけではないってことなんですね。

久保 上席研究員
そうですね。
情報通信技術が発達する以前は、仕事が終わって職場を離れたら心理的にも仕事から
距離がとれたのですが、今はスマートフォンがあるのでなかなか難しい状況です。
そのような状況だと、常に仕事に拘束されやすくなってしまいます。
たとえば、帰宅してからメールなどで仕事の連絡があった場合、そして特にその連絡の内容が嫌な内容だった場合、仕事のことが気になって眠れなくなったりするといったことが
読者の方々もご経験あるのではないでしょうか?
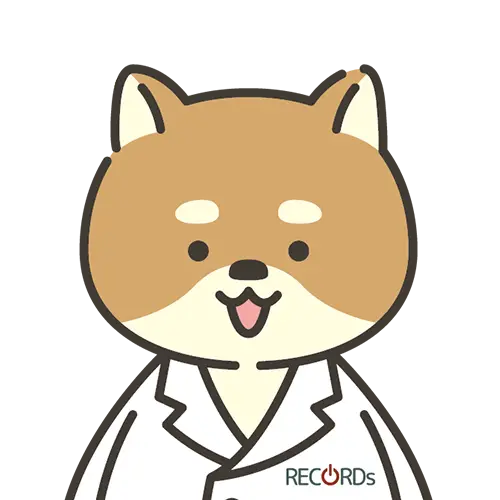
あんえい犬
うん、確かに、ぼくでもあります。
ところで、「つながらない権利」って、日本で法制化することはあり得るんですか?

久保上席研究員
ガイドラインとして勤務時間外の連絡を制限するようなことは触れられていますが、
法制化するには色々なハードルがあるので「分からない」というのが正直なところです。
でも、勤務時間外での労働はそもそも現在の労働基準法でも制限されているので、
現行の法律を遵守することで「つながらない権利」が守られていると考えることもできます。
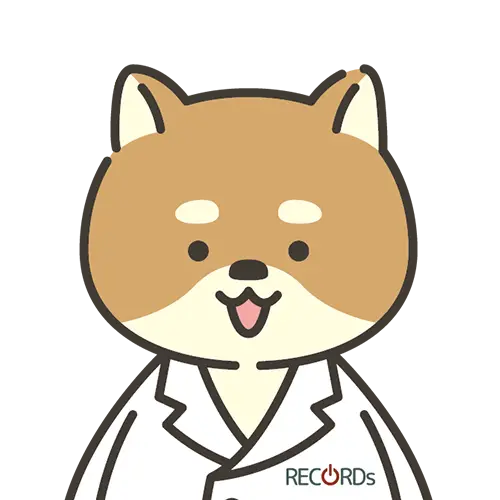
あんえい犬
すでにある法律でも守られるはずってことですね。

久保上席研究員
そう。あくまで法律上はそういう考え方もあります。
あと、こんな風に考えることもできると思います。
「なぜ、勤務時間外の仕事の連絡が問題になるのか?」というそもそもの問題を考えた場合、
その答えは勤務時間外の仕事の連絡が単純に嫌だからだと思います。
プライベートの時間が侵食されるのはもちろんあると思いますが、上司や同僚、顧客からの
嫌な連絡をプライベートに受けたくないからというのが問題の根底にあるのだと思います。
したがって、「つながらない権利」は労働時間管理という側面とともに
ハラスメントの問題としても捉えられるのではないでしょうか?
ハラスメントに関しては、もうすでにハラスメント防止に関する法律があるので、
もしかしたらその枠組みの中でも考えられるかもしれませんね。
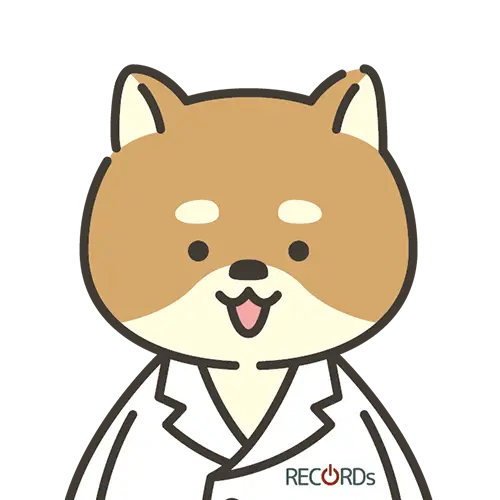 あんえい犬
あんえい犬
海外ではどうなってるんですか?

久保上席研究員
フランスで法制化されたのを皮切りにしてEU全体あるいはアメリカ、カナダの一部の州、
オーストラリア等、様々な国で法制化されてます。ただ、その法制化の内容は様々です。
労働政策研究・研修機構の山本陽太先生によれば、次の5つのタイプがあるそうです。
①不利益な取り扱いを禁止
②労働時間外の連絡を禁止
③具体的な時間帯を明記することを義務化
④法律の中で具体的な措置を定める
⑤企業内ポリシーの策定を義務化
様々な職場で働き方などが異なるため、一律に勤務時間外の仕事の連絡を禁止した場合、
必ず抜け穴を通って絵に描いた餅になってしまうと思います。
(詳しくは → こちら)
どのような「つながらない権利」の導入が健康確保に有効かを議論して各職場単位などで
カスタマイズしていく継続的なプロセスが重要だと個人的には考えています。
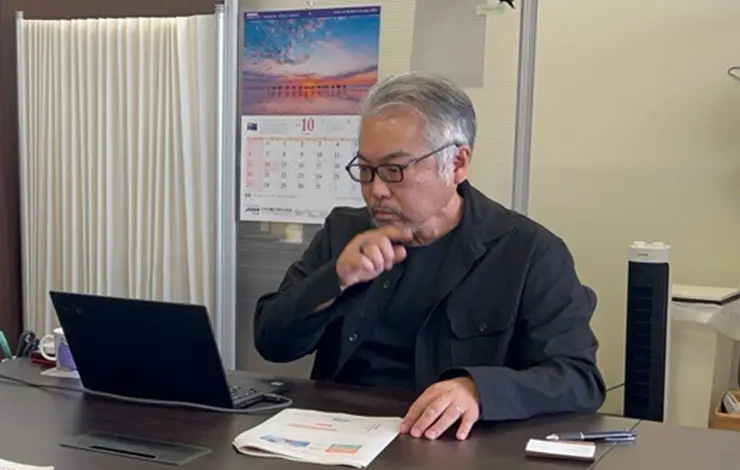
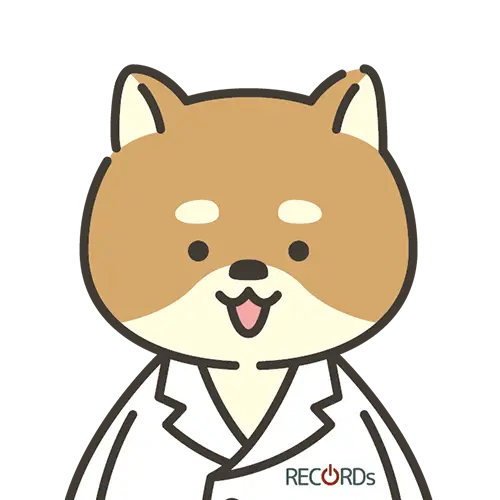
あんえい犬
海外と日本では文化も違うので、日本の働き方やライフスタイルに合った方法を取り入れる
必要がありそうですね。一筋縄でいくものではなさそう・・・
どんな対処法があるのか、自分でも考えてみます!

久保上席研究員
最近、色々な所で取り上げられているから、調べてみると勉強になるよ!
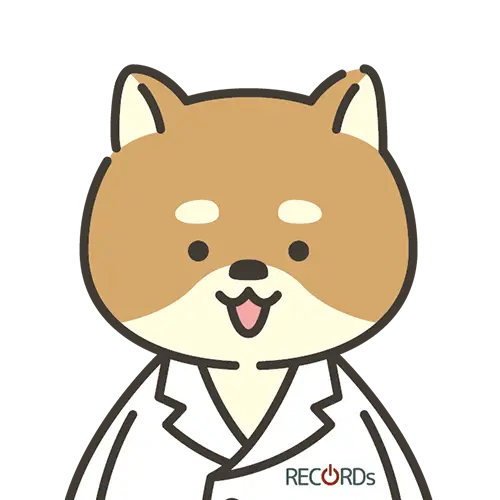 あんえい犬
あんえい犬
情報につながるのは自由だからね!
次回は、「具体的にできそうなこと」教えてください!
つづきはこちら ⇒ 「File#3」