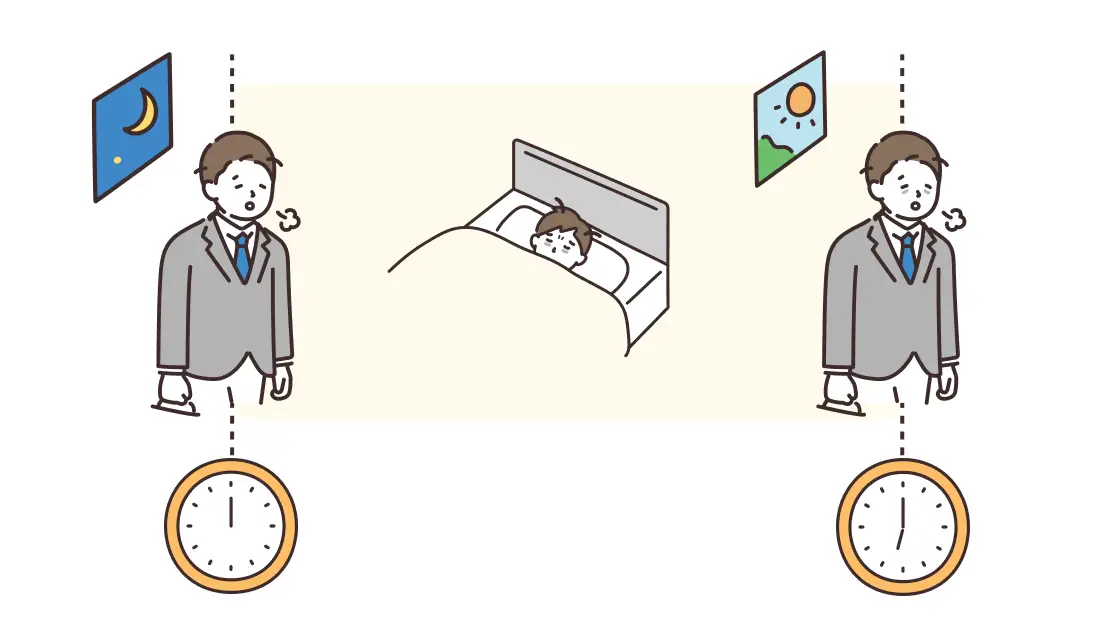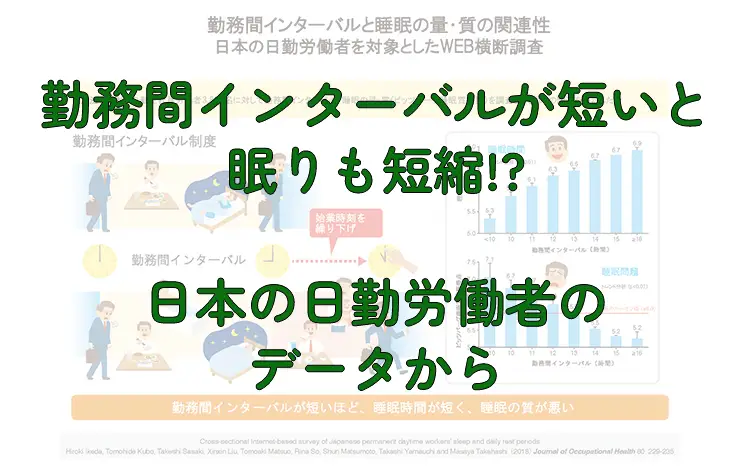勤務間インターバル、睡眠時間と病気欠勤の関連:日本の日勤労働者を対象とした1年間のコホート研究

出典論文
Ikeda H, Kubo T, Izawa S, Nakamura-Taira N, Yoshikawa T, Akamatsu R, Joint association of daily rest periods and sleep duration with sick leave: a one-year prospective cohort study of daytime employees in Japan, Industrial Health, 2025, Volume 63, Issue 2, Pages 206-212, https://doi.org/10.2486/indhealth.2024-0069
著者の所属機関
論文の内容
勤務間インターバルとは、勤務終了から翌始業までの休息期間のことを言います。これまでの研究で、短い勤務間インターバル(特に11時間未満)が健康や生産性に悪影響を及ぼすことが報告されていましたが、勤務間インターバル内に含まれる睡眠時間も健康や生産性と関連することが報告されています。本研究では、勤務間インターバルと睡眠時間の組み合わせ(両方が短い、勤務間インターバルは長くとも睡眠時間は短いなど)と病気欠勤との関連を、日本の日勤労働者を対象にした1年間のコホート調査から検討しています。ベースライン調査と1年後の追跡調査の両方に参加した5,593名(女性2,243名,平均年齢45.1歳)を分析対象とし、ベースライン調査時の「勤務間インターバル」と「睡眠時間」、追跡調査時の「過去1年における病気休暇(なし、1日以上1週間未満、1週間以上1か月未満、1か月以上)」の関連をロジスティック回帰分析で検討しました。その結果、一定の勤務間インターバル(15時間)と睡眠時間(6時間以上)を確保していた群と比べて、睡眠時間の長短(6時間以上、未満)に関わらず勤務間インターバルが短い(11時間未満)群は、長期(1ヶ月以上)の病気欠勤のオッズ比が有意に高くなっていました。なお、短期(1日~1週間)、中期(1週間~1か月)の病気欠勤との関連は見られませんでした。このことは、短い勤務間インターバルがその後の長期の病気欠勤と関連することを示しており、この対策として勤務間インターバル制度により一定の勤務間インターバルを確保できれば、長期の病気欠勤のリスクを低減できる可能性が考えられます。
RECORDsメンバーによる解説
本研究から、短い勤務間インターバルがその後の長期の病気欠勤につながる可能性が示されています。一方で、論文で報告された95%信頼区間は広く、その背景には勤務間インターバルが普段から11時間を切るような労働者や長期病気欠勤の経験者が少ない(どちらも全体の1%)ことが原因としてあげられます。短・中期の病気欠勤も含めて、短い勤務間インターバルの影響を安定して確認するには相当なサンプルサイズが必要となることがうかがえます。
また、国外の先行研究(Vedaa et al., 2017)では、11時間未満の短い勤務間インターバルが短期の病気欠勤と関連することが報告されています。一方、日本の日勤労働者を対象とした本研究では、短期の病気欠勤との関連は見られませんでした。この背景として、労働や休むことに対する文化的・社会的な違いがあると考えられます。例えば、国外には病気欠勤による補償がある国もあり、上記の先行研究が行われたノルウェーでは、病気欠勤において傷病手当が得られるようです(https://www.nav.no/sykepenger/en)。一方、日本は病気欠勤に関する法的制度はなく、また健康保険の傷病手当はあるものの期間や補償額の制限、申請の手間があるためか、風邪をひいても休めない・休まないという人が少なくないという調査報告があります。そのため、日本は他国と比べて病気欠勤率が低いことが報告されています。また、特に勤務間インターバルが短い(長時間労働で忙しい)人は、(仕事が終わらないから、人に迷惑をかけるからなどの理由で)休みたくても休めない、休まない方が多いのかもしれません。このような違いが研究結果に表れたと考えられます。