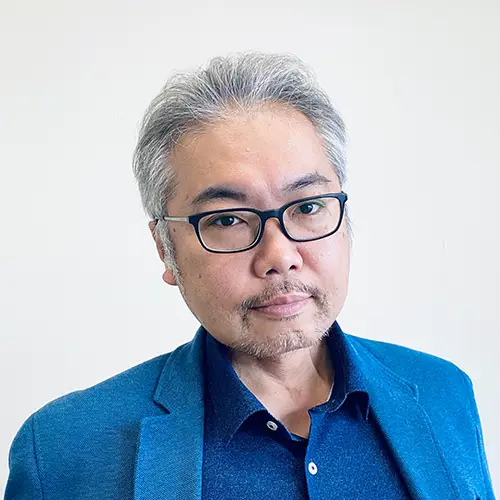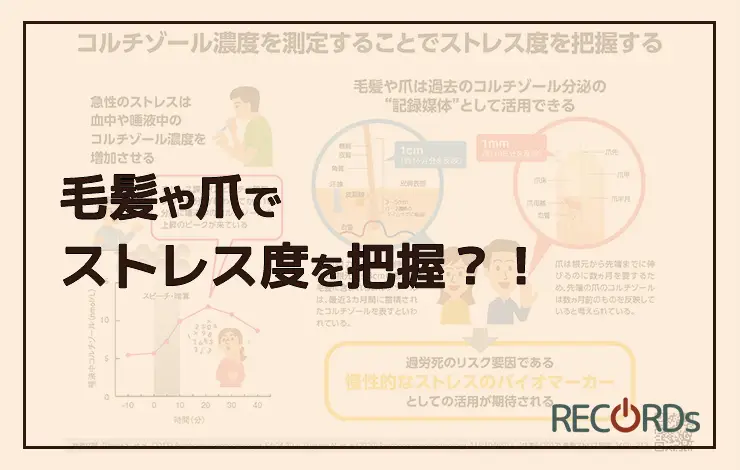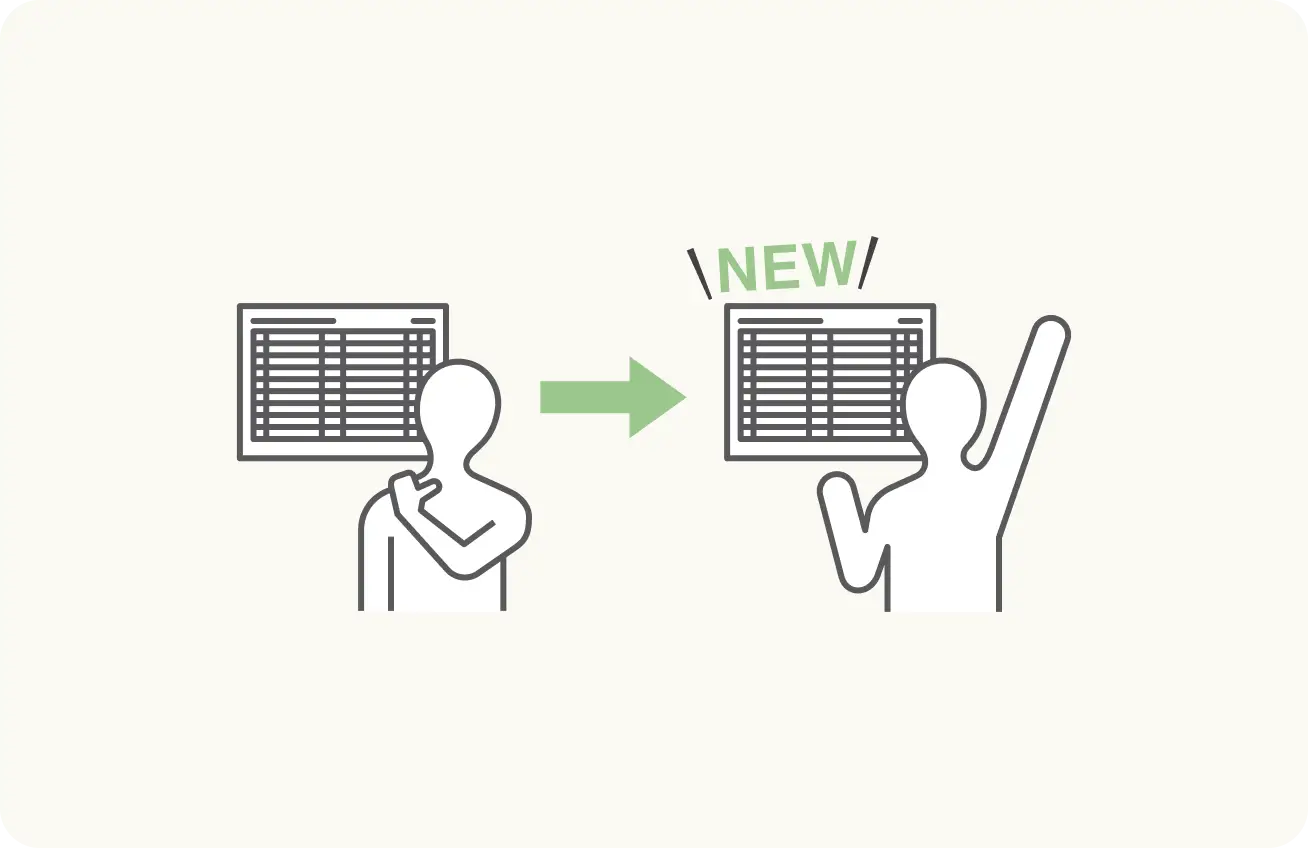職場の疲労に関する測定ツールまとめ
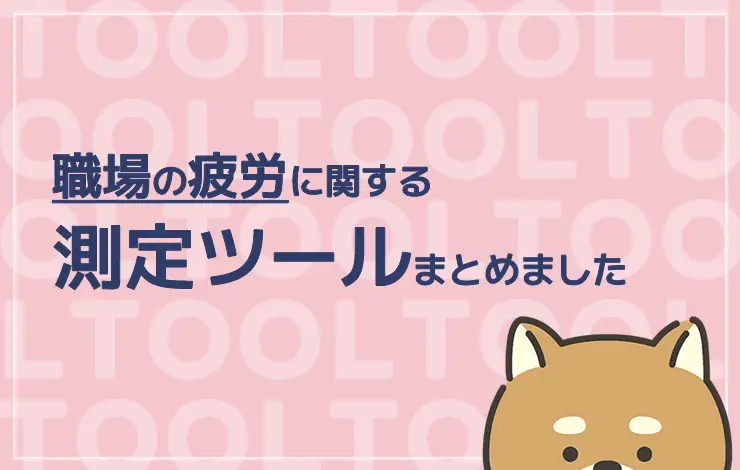
職場環境の改善に役立つ、無料で利用できるツールをご紹介します。
日々新しいツールが登場していますので、今後も最新情報を随時追加していく予定です。
自覚症しらべ
日本産業衛生学会の産業疲労研究会が作成した自記式の調査票です。
使用方法は出勤時、昼休みの前後、退勤時、就寝前等のように経時的に測定する方法が推奨されています。種類の異なる5つの疲労の因子(ねむけ感、不安定感、不快感、だるさ感、ぼやけ感)の経時的な変化を働き方と結びつけて調べることで疲労対策のヒントが得られます。無料でお使いいただけます。
労働者の疲労蓄積度自己診断チェックリスト
(2023 年改正版)
この調査票はこれまで過重労働面談において広く活用されてきた疲労蓄積度自己診断チェックリストが2004年の旧版以降の働き方の変化に対応して2023年に作成された改正版になります。この改正版も従来と同じように自身の疲労状態と働き方の2側面から疲労蓄積度を評価するツールになっています。また、本調査票には家族版も用意されています。ご自身のご家族の方の疲労度が気になる方はこちらの調査票を使ってご家族の方の疲労度をチェックしてみて下さい。
WEB上で測定可能な新版の疲労蓄積度チェックリスト
◇ 労働者の疲労蓄積度自己診断チェックリスト」(2023年改正版)(働く人用)
⇒ こちら
◇ 労働者の疲労蓄積度自己診断チェックリスト」(2023年改正版)(家族支援用)
⇒ こちら
修正版開発の経緯
労働者の疲労蓄積度自己診断チェックリスト改正版の開発の経緯について、詳しく説明しています。 ⇒ こちら
過労徴候しらべ
過労死として労災認定された際の調査復命書の中に記載されていた実際に被災された方の前駆症状を活用して、過労リスクを簡便に測定し、過労死や過重労働による健康障害の予防につなげる目的で作成された調査票です。
この調査票ではさまざまな過労症状を過去6か月、振り返って尋ねるので、ある程度、長期間のスパンをおいて経年的に従業員の過労状態を尋ねることをお勧めいたします。調査票にはこれ以上、得点が高いとリスクが高いという基準値は今のところありませんが、経年的に追うことで前回調べた時と比べて高くなる従業員や、平均値でまとめた部署の得点が高くなった場合には過労リスクを低減させる対策が重要です。また、調査項目の中には重篤なものも含まれているので総合得点だけではなく、ここの得点にも配慮して過労リスク対策を検討して下さい。
◇ 過労リスクを評価する「過労徴候しらべ」調査票
⇒ こちら