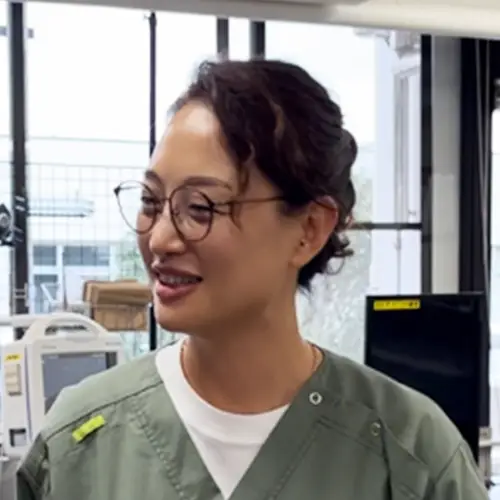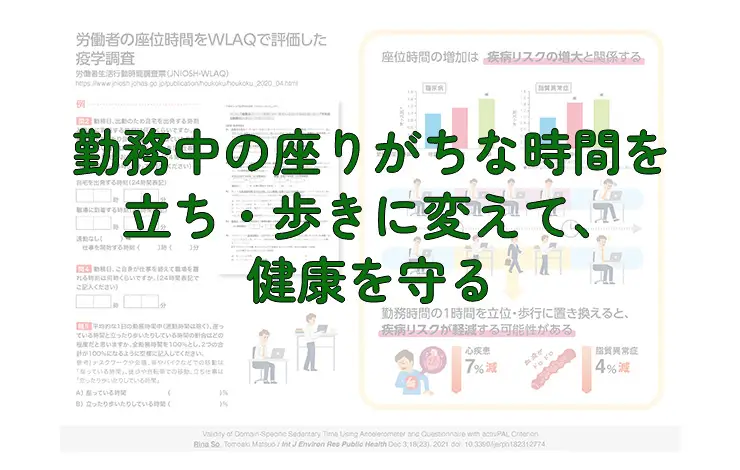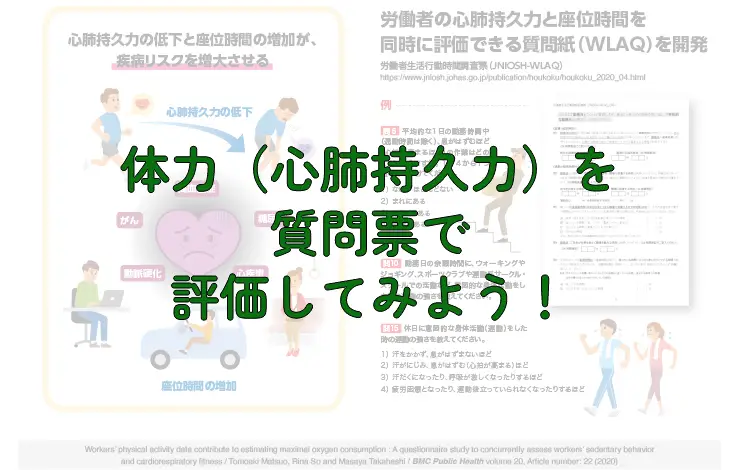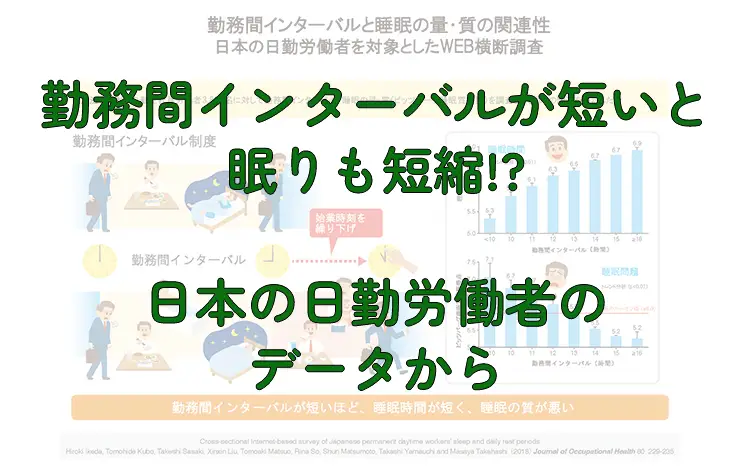生活習慣と死亡リスクの関連を調査:UKバイオバンクから見えた睡眠・身体活動・食事のバランス

出典論文
Stamatakis, E. et al. (2025). Minimum and optimal combined variations in sleep, physical activity, and nutrition in relation to all-cause mortality risk. BMC Medicine, 23:111.
https://doi.org/10.1186/s12916-024-03833-x
著者の所属機関
Emmanuel Stamatakis、エマニュエル・スタマタキス(筆頭著者)
Mackenzie Wearables Research Hub, Charles Perkins Centre, The University of Sydney, Sydney, NSW, Australia、オーストラリア・シドニー大学
論文の内容
この研究は、睡眠・身体活動・栄養(食事の質)という3つの生活習慣(SPAN:Sleep, Physical Activity, and Nutrition)の組み合わせが、全死因死亡リスクとどのような関連を持つかを検討したものです。対象となったのは、イギリスのUKバイオバンクに登録されている59,078人で、腕時計型のウェアラブルデバイスにより睡眠時間と身体活動量を7日間連続して測定し、さらに食事内容はアンケートによってスコアで評価されました。
解析の結果、睡眠が7.2〜8.0時間/日、身体活動が42〜103分/日、食事スコアが57.5〜72.5点であった群では、睡眠5.5時間/日、運動7.3分/日、食事スコア36.9点の群と比較して、死亡リスクが有意に64%低いという結果が得られました(ハザード比0.36)。ハザード比(HR)は、時間の経過を踏まえて比較群と相対的にリスクを比較する指標であり、HR=1.00が同程度、HR<1.00は特定の期間における死亡の起こりやすさが相対的に低いことを意味します。
特に興味深い点として、15分の睡眠延長、1.6分の中高強度身体活動の追加、食事スコアの5点向上(例:野菜を1/3カップ増やすなど)といった比較的小さな生活習慣の違いで、10%の死亡リスクの差が示されたことです。さらに、睡眠を75分延ばし、中高強度身体活動を12.5分追加し、食事スコアを25点向上させると、死亡リスクは約70%の差が見られました。また、睡眠・身体活動・食事をいずれか単独で改善するよりも、3つをバランス良く組み合わせた場合に死亡リスク低下との関連がより強くなることが示されました。つまり、「睡眠時間を増やすだけ」「完璧な運動習慣だけ」「理想的な食生活だけ」といった単独の行動ではなく、3つの行動すべてを少しずつ意識し、バランスよく取り入れることが、健康リスクとの関連を小さくする可能性が示唆されています。
RECORDsメンバーによる解説
著者は、これまでWHOの身体活動ガイドライン作成に関わった専門家として、身体活動と健康に関する研究を多数発表してきました。今回の研究では、その豊富な知見をもとに、「生活サイクル」という枠組みから生活習慣を捉え直しており、これは非常に興味深い着眼点であると思います。
本研究は、過度な生活改善を求めるのではなく、「睡眠・身体活動・栄養」の3つの行動を少しずつ組み合わせて改善することで、死亡リスクを実際に下げられる可能性があるという新たな視点を提供しています。私たちの24時間は、余暇、職場、睡眠という大きな領域に分けて考えることができます。それぞれの領域での身体活動の量や質、栄養状態は互いに影響し合い、さらに睡眠の質や長さにも密接に関わっています。この記事を読まれている皆さんにも、こうした相互作用は実感として理解できるかもしれません。ただ、これらをどのように構成し、どの程度改善すればよいのかについては、断片的な研究はあっても、総合的な指針はまだ十分に示されていません。長時間労働や不規則勤務を介した睡眠、活動、食生活が乱されることによる健康への影響を考慮すると、本研究は、生活習慣を統合的に見直すことの重要性を示唆していると言えます。
特に、長時間勤務が常態化している日本の働き方においては、「どのくらい睡眠を取るべきか」「どの程度身体活動を維持すべきか」といった、生活習慣に関する最低限必要な基準(閾値)を明確にし、それを余暇・職場・睡眠といった生活領域ごとに意識しながら整えることが必要であると思います。そして、得られた基準を社会全体で共有し、実践に結びつけることが、過労死防止に向けた重要なステップになると考えます。
過労死等防止調査研究センターには、多様な専門分野の研究者が集まっています。今後は、これまでの知見をさらに統合し、生活領域全体を視野に入れた生活習慣改善を目指した調査研究に取り組み、過労死予防に直結する実践的で具体的な知見の構築を進めていきたいと考えています。